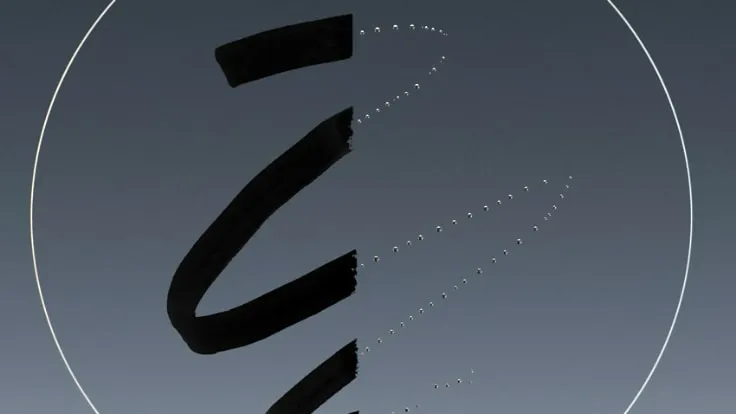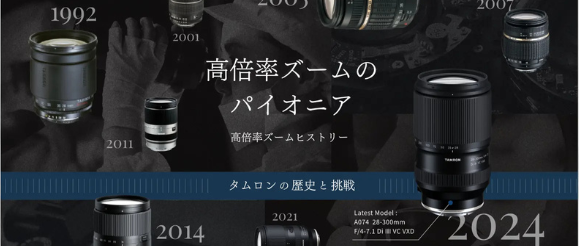2024.08.30
カメラ用レンズのお手入れ・クリーニング方法【季節別の注意点もご紹介】
カメラ用レンズのお手入れ・クリーニング方法【季節別の注意点もご紹介】


レンズのお手入れにはいくつかの道具が必要です。ブロアー、レンズクロス、レンズクリーナー液など基本的なクリーニング用のアイテムを揃えておきましょう。
ブロアー
ブロアーは、レンズ表面やカメラ本体に付着したチリやホコリなどの微粒子を吹き飛ばすための必須アイテムです。レンズを傷つけないためにも、クリーニングの最初のステップとして必ず使用しましょう。
ブロアーにはいくつか種類がありますが、手で握って吹きかけるタイプのブロアーがおすすめです。吹き出す空気の強さを自分でコントロールできるため、レンズに優しいクリーニングできます。エアダスターのような缶タイプもありますが、強すぎる空気圧でレンズを傷つけたり、内部に水分や不純物が入り込む可能性もゼロではありません。使うときは注意してください。
レンズクロス
レンズクロスは、カメラ本体やレンズの鏡筒を拭き上げるのに使用します。マイクロファイバー製のクロスは非常に細かい繊維で作られているため、傷をつけにくく効果的に汚れを落とすことができます。
また、繰り返し洗って使えるものを選ぶと経済的です。使用後のレンズクロスは、適切な方法で洗濯と乾燥をしましょう。ホコリや汚れが付着しないように、清潔な場所で保管することも重要です。
レンズクリーナー液
レンズクリーナー液は、レンズの汚れを落とすための専用の液体です。いろいろなタイプがありますが、カメラレンズ専用のものを選びましょう。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
また、クリーナー液を使用する際は、レンズに直接つけるのではなく、必ずクリーニングペーパーやクロスに少量を染み込ませて使用するようにしましょう。
レンズクリーニングペーパー
レンズクリーニングペーパーは、レンズ表面を拭き取るための専用のペーパーです。一般的なティッシュペーパーなどとは異なり、繊維くずが出にくく、レンズを傷つけない素材でできています。
ペーパーは使い捨てなので、毎回新しいものを使用することで、前回のクリーニングで付着した汚れを再びレンズにつけてしまう恐れがありません。
使用する際は、ペーパーを折りたたんで清潔な面を使い、レンズの中心から外側に向かって円を描くように優しく拭いていきます。
クリーニングの手順
レンズのクリーニングは、ブロアーで細かい粒子やホコリを取り除いてから、クリーナーで拭き上げていきます。ここでは、クリーニングの手順を詳しくご紹介します。
①ブロアーで細かいチリやホコリを飛ばす
ブロアーでホコリを除去した後、レンズの前面(前玉)を拭き上げます。この際、レンズクリーニングペーパーにクリーナー液を少量つけ、レンズの中心から外側に向かって渦を描くように拭き上げていきます。
拭き上げる際は、決して強く押し付けないようにしましょう。レンズに軽く触れる程度の力加減で、優しく拭き上げることが大切です。強い力をかけると、レンズのコーティングを傷つける可能性があります。
注意点として、防汚コートが施されているレンズの場合は、クリーナー液を使用するとコーティングが剥がれてしまう恐れがあります。このような場合は、クリーナー液を使用せずに、乾拭きのみ行うようにしましょう。
③レンズ後面(後玉)を拭き上げる
レンズの後面(後玉)も、前面と同様の方法で拭き上げます。
同時に、マウントの接合部も掃除をしましょう。ここはレンズ交換の際に指で触れることがあるため、汚れが付着しやすい箇所です。レンズクロスや綿棒を使用して丁寧に拭き上げましょう。その際、接点部分を指で触って皮脂などが付着しないよう注意が必要です。
④鏡筒部(レンズボディー)を拭き上げる
最後に、レンズの鏡筒部(レンズボディー)のクリーニングを行います。まず、ブロアーを使用して、ズームリングやフォーカスリングの溝の中に入り込んだチリやホコリを吹き飛ばします。
その後、レンズクロスを使用して鏡筒部全体を乾拭きします。この部分はクリーナー液は使用せず、乾拭きのみで十分です。ただし、ボディーの素材によっては傷がつきやすい場合もあるので、強くこすりすぎないよう注意しましょう。また、ズーミングで全長が変化するレンズは一番伸ばした状態で鏡筒部分を優しく乾拭きしてください。
クリーニングの頻度
レンズのクリーニング頻度は、使用状況や環境によって異なります。過剰にクリーニングをすると逆効果になる恐れがあるため、頻繁に行う必要はありません。
目に見える汚れが付着した場合は、その都度クリーニングを行うことをおすすめします。たとえば、指紋が付いてしまった場合や、風が強い日の屋外で撮影した場合、海岸や砂漠のような乾燥した地域や汚れやすい環境で撮影した場合などは、その日のうちにクリーニングを行いましょう。
定期的なメンテナンスとしては、2〜3か月に一度くらいのペースでクリーニングを行えば十分でしょう。ただし、目立った汚れがない場合は、クリーナー液を使用せず、乾拭きのみでOKです。
レンズの保管方法
レンズを長く使うためには、レンズの保管方法もクリーニングと同様に重要です。正しい環境で保管することで、レンズの寿命を延ばすことができます。
高温多湿を避け、風通しの良い場所に
レンズにとって一番の大敵は、ホコリと湿気です。これらはレンズを傷める原因となるため、できるだけ避けるように管理することがポイントです。だたし、無闇に湿度を下げると、レンズのグリスやゴム、コーティングなどの劣化を招く恐れもあります。そのため、湿度の目安としては、40〜50%程度を維持するようにしましょう。この範囲であれば、カビの発生を防ぎつつ、乾燥によるレンズの傷みを避けられます。
また、風通しの良い場所を選ぶことで、ホコリやゴミがたまりにくくなります。直射日光もレンズを劣化させる原因となるため、日の当たらない場所に保管しましょう。その他、エアコンなど空調の風が直接当たる場所も避けたいところです。急激な温度変化でレンズ内部に結露を引き起こす可能性があるためです。
可能であれば、防湿庫を利用できると便利ですが、なかなか難しい場合もあるでしょう。防湿庫が用意できない場合は、ドライボックスに乾燥剤を入れて、湿度計で湿度を管理しましょう。
乾燥剤を使用するときの注意点
シリカゲルなど乾燥剤は湿気対策に有効ですが、使用する際は使いすぎに注意しましょう。使いすぎると湿度が過度に低下し、前述の通りかえって好ましくない環境になってしまいます。湿度計を設置して、適度な湿度(40〜50%程度)を維持するよう心がけましょう。
また、乾燥剤の有効期限にも要注意です。期限を過ぎた乾燥剤は湿気を吸収する能力が低下し、逆に湿度を高くする原因になります。必ず有効期限内のものを使用し、期限が来たら新しいものと交換してください。
防湿庫に保管するときの注意点
まず、適切な湿度設定にすることが重要です。繰り返しになりますが、40〜50%程度の湿度が目安です。湿度を下げすぎないよう、注意してください。
また、レンズを保管する際は、必ずカメラボディから取り外して保管しましょう。カメラボディとレンズを接続したまま保管すると、接点部分に湿気がたまりやすくなります。さらに、フィルター類も外し、前後のキャップをつけた状態で保管することが大切です。
定期的に取り出して操作する
レンズを長期間使用しない場合でも、定期的に取り出して動かすようにしましょう。2〜3か月くらいを目安に、レンズを保管場所から取り出し、フォーカスリングやズームリングを操作するのがおすすめです。この作業により、レンズ内部の空気を入れ替え、湿気がたまりにくくなります。
また、定期的に触ることで、レンズの動作確認にもなります。その際、もし動作に違和感を覚えたら、メーカーのメンテナンスサービスに出すことも検討しましょう。
【季節別】よくあるトラブルと対策方法
気候によってレンズのトラブル原因も変わってきます。たとえば、カビは湿気の多い梅雨の典型的なトラブルですが、寒暖差のある夏や冬にも発生しやすいです。それぞれのシーズン特有の問題を知って、レンズへのダメージを未然に防ぎましょう。
【春】花粉や黄砂の対策方法
春は花粉や黄砂など、微細なチリやホコリの影響を受けやすくなります。こうした粒子は非常に小さく、レンズ表面や細部に付着します。
特に春は風が強く吹くことも多く、砂埃が舞い上がり、レンズにも入り込みやすくなりがちです。とくに風の強い日の撮影では、使用していないときはレンズキャップをつけておきましょう。
また、外で撮影した後、特に砂地や野山などから帰ってきた場合は、こまめな手入れが重要です。撮影後はレンズをブロアーで清掃し、必要に応じて軽く拭き上げることをおすすめします。
【梅雨や夏、冬】結露やカビの対策方法
梅雨から夏にかけての高温多湿の時期、そして冬の寒冷期は、レンズにとって特に注意が必要な季節です。この時期に最も警戒すべきは、結露とそれに伴う水ヤケやカビの発生です。これらの問題がレンズに発生すると、撮影された写真が白っぽくモヤがかかったように見える場合があります。そのため、防カビのためのメンテナンスや適切な保管方法に十分注意を払うことが重要です。特に冬は室内外の気温差が大きく結露が発生しやすいので、注意が必要です。
カビの発生原因
カビの発生プロセスを知っておくと、対策も立てやすくなります。カビの主な原因は急激な温度変化による結露です。たとえば、屋内と屋外、平地と高地など、気温が高い場所から低い場所へ移動する際にレンズの内部や表面に結露が発生しやすくなります。
この水滴が長時間付着したまま残ると、白っぽい汚れとして沈着し(水ヤケ)、さらにホコリが付着すると「ヤケ」と呼ばれる状態になります。そして、ヤケの状態で放置されると、最終的にカビが繁殖するのです。
カビが発生した状態からレンズを元の状態に戻すことは非常に困難で、レンズの買い替えが必要になるケースも少なくありません。そのため、カビの予防はレンズの寿命に直結します。
カビを未然に防ぐために
カビの発生を防ぐためには、気温変化とレンズの保管方法に注意しましょう。
まず、急激な気温差を避けることが重要です。暑い場所から寒い場所へ移動する場合は、すぐにレンズを取り出さないようにしましょう。代わりに、レンズをケースやポーチに入れたまま、しばらく周囲の気温になじませてから取り出すようにします。これにより、レンズ表面や内部に結露が発生しにくくなります。特に注意が必要なのは、寒冷地や山中での撮影です。暑い場所から寒い場所に移動する際は、レンズヒーターを使用するのも手です。レンズヒーターは、レンズの温度を一定に保ち、結露を防ぐ効果があります。
また、レンズの保管方法も重要です。前述の通り、保管庫や乾燥剤を適切に使用してちょうど良い湿度をキープするようにしてください。
さらに、定期的なメンテナンスも欠かせません。使用後はレンズを清掃するほか、あまり使用していない場合でも、前述の通り定期的に触ってレンズ内の空気を入れ替えましょう。
注意したい撮影場所
撮影場所によっては、レンズへの配慮が必要な場合があります。ここでは、特に注意が必要な撮影場所とその対策について詳しく見ていきましょう。
水辺や海、冬山
水辺や海、冬山など自然環境での撮影は魅力的な反面、レンズにとっては過酷な条件となります。
まず、撮影を終えて家に帰ったら、レンズの鏡筒を最大限に伸ばし、全体を丁寧に拭き上げましょう。この際、レンズクロスを使用し、結合部や溝などの細部まで注意深く拭きます。その後、十分に乾燥させてから保管することが大切です。
特に海での撮影後は海水が飛沫として付着し、塩分でレンズが傷む可能性があります。そのため、丁寧な拭き上げを怠らないようにしましょう。
冬山での撮影後は、結露に注意が必要です。寒冷地から暖かい室内に戻った際に急激な温度変化が起こるため、レンズケースに入れたまましばらく置き、徐々に室温になじませてからクリーニングを行いましょう。
運動場や砂浜
運動場や砂浜など、砂やホコリの多い環境での撮影では、微細な粒子がレンズの隙間に入り込みやすくなります。
このような場所での撮影後は、まずブロアーを使用して細部までしっかりとホコリや砂を吹き飛ばすことが重要です。特に、ズームリングやフォーカスリングの周辺、レンズマウント部分など、砂粒がたまりやすい箇所に注意を払いましょう。
ブロアーでの清掃後、通常のクリーニング手順に従って丁寧に拭き上げを行います。この際、砂粒が残っていないか十分に確認しながら作業を進めることが大切です。砂粒が残ったまま拭くと、レンズ表面やズームリングなどの可動部に傷をつけてしまう可能性があるためです。
また、砂浜など砂埃の舞いやすい環境での撮影時は、できるだけレンズ交換を避け、必要最小限の機材で撮影することをおすすめします。
防汚コートや防滴構造が施されたレンズを選ぶ
防汚コートは、レンズ表面に施された撥水性・撥油性に優れたコーティングです。このコーティングにより、水滴や指紋、ホコリなどの汚れが付きにくくなり、付着しても簡単に拭き取ることができます。特に雨天時や湿度の高い環境での撮影時に、非常に頼りになります。
また、防滴構造を持つレンズは、レンズ内部へ水滴が侵入しにくい設計になっています。これにより、多少の雨や水滴であれば、レンズ内部に入り込むリスクを低減できます。ただし、完全防水ではないため、悪天候下ではレインカバーを使用しましょう。
タムロンレンズ点検サービスのご案内【会員登録でお得に!】
タムロンではお客様にレンズを長く、快適に使用していただくために、タムロンレンズ点検サービスを提供しています。このサービスでは、経験豊富な専門スタッフがお客様のタムロンレンズの動作点検や各部の清掃、ファームウェアのアップデートまで実施いたします。
ー 会員ランクに応じて修理価格を割引
さらに、ご愛用のタムロンレンズにトラブルが発生した場合でも、タムロンの会員サービス「TAMRON ID」にご登録いただければ、会員様限定の修理料金割引をご利用いただけます。安心して長くお使いいただくためにも、この機会にぜひご登録ください。
<まとめ>適切なメンテナンスでレンズを長く大切に使おう!
レンズを長く大切にお使いいただくためには、日々のメンテナンスが欠かせません。この記事でご紹介したようなケアを定期的に行うことで、レンズの性能を長期的に維持し、思い通りの写真を撮り続けることができます。万が一レンズに異常を感じたら、メーカーのメンテンナスサービスの利用も検討してみましょう。