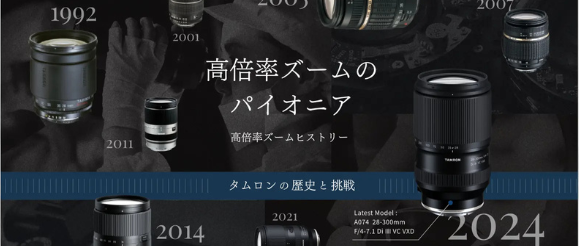2025.08.29
光芒・光条とは?発生する仕組みや撮り方のコツを解説
光芒・光条とは?発生する仕組みや撮り方のコツを解説



光芒は、特に太陽光の強い逆光条件などで見られる、やわらかい霧状・煙状の光の帯のことを指します。太陽光が、空から降り注ぐ光のカーテンのように見える現象です。森林の朝日や山間部の夕景など、自然環境で特に美しく現れます。この光芒は「薄明光線」とも呼ばれ、風景写真で神秘的かつ幻想的な雰囲気を演出してくれます。
光芒が表れる仕組み
光芒は、太陽光が雲や空気中の微粒子、木などで散乱することで発生します。特に朝夕の斜光に霧や水蒸気があると、光の柱が美しく現れやすくなります。この現象により、写真にドラマチックな印象を与えることができるでしょう。
光条とは?

光条は、点光源から放射状に伸びる光の筋を表す現象です。夜景の街灯や太陽のスター・バースト効果が代表的な作例となります。光条をうまく活用することで、写真にアクセントを加え、より印象的な作品をつくることができるでしょう。
太陽が画面内に入る場合は、カメラのイメージセンサーやレンズ内部にダメージを与えないためにも、長時間同じ箇所に太陽を置かず構図決定を早くし短時間の撮影にとどめる必要が有ります。特に夏場の高温時は太陽の直射を避け、撮影しないときは日陰へ移動しレンズキャップ装着が必須です。
光条が表れる仕組み
光条は、レンズの絞り羽根によって光が回折することで発生する現象です。太陽や街灯などの強い点光源を、F8からF16程度に絞って撮影すると顕著に現れやすくなります。絞り羽根の枚数が偶数の場合、光条の本数は羽根の枚数と同じになり、奇数の場合はその2倍になるという特徴があります。たとえば、6枚羽根なら6本、7枚羽根では14本の光条が現れます。また、円形絞りを採用したレンズでは、開放から4~5段以上絞ることで、光条がよりはっきりと現れる傾向にあります。
光芒や光条の撮影に適した機材
光芒や光条を美しく撮影するために、機材選びで考慮しておきたいポイントを解説します。
カメラ本体
ダイナミックレンジが広いカメラは、明るい部分から暗い部分までの階調を豊かに描写することができます。光芒撮影では明暗差が大きくなりがちなため、白飛びや黒つぶれを抑制できるカメラが理想的でしょう。また、高感度性能に優れたカメラは夜景での光条撮影時にノイズを抑えやすく、クリアな光の筋を表現できます。手ブレ補正機能があると、薄暮時や早朝の撮影でも手持ちでの撮影が可能になり、シャッターチャンスを逃しにくくなるでしょう。
レンズ
被写体によって異なりますが、雲間からの光芒撮影では刻々と状況が変化するため、ズームレンズがおすすめです。広角ズームレンズや標準ズームレンズを使って風景を撮影してみましょう。逆光での撮影になるため、フレアやゴーストが抑制されたレンズを使用することで、よりクリアな光の表現が可能になります。
一方、光条は絞りを絞り込むことで発生しやすくなり、主に夜景の撮影でアクセントとしてよく活用されます。絞り羽根の形状に角があると、より光条はシャープに現れますが、円形絞りのレンズでも絞り込むことで光条をつくり出すことが可能です。
三脚やフィルター
足場が不安定な場所や、夜景などの撮影では、三脚を使用しましょう。光芒撮影では遅めのシャッタースピードを設定することもあるため、手ブレを防ぐためにも三脚があると便利です。また、日中の撮影では、適宜ND(減光)フィルターを使用することで、適切な露出設定が可能になります。海の撮影などでは、PL(偏光)フィルターを使用することもありますが、状況によっては偏光効果が効きすぎて光芒を弱めてしまう場合もあるので、注意しましょう。
光芒を撮影するコツ
ここでは、光芒を美しく撮影するためのコツをご紹介します。自然現象であり、光芒は、時間帯や天候の影響を大きく受けるため、計画的なアプローチが大切です。事前に代表的な撮影ポイントを調べて、条件の良いタイミングで撮影にチャレンジしてみるのもおすすめです。
時間帯や気象条件に気をつける

光芒撮影において特に重要なのは、適切な時間帯と気象条件を選ぶことです。早朝や夕方の斜光時は、太陽の角度が低く、光の柱が美しく現れやすい最適な時間帯となります。霧や水蒸気が多い日は光の筋がより立体的に見えるため、特に狙い目でしょう。前日との寒暖差が大きい日の朝は霧が発生しやすく、絶好の撮影チャンスとなります。天気予報をチェックし、湿度や気温差を確認することが重要です。
撮影ポイントを下調べする
光芒の撮影で失敗しないためには、事前の下調べが欠かせません。太陽の位置や光の方向を予測し、撮影場所を決めておくことで、限られた時間の中で効率的に撮影できるでしょう。地形や木々の配置から光の柱が現れる方向を想定し、複数の候補地を用意しておくのがおすすめです。当日の気象条件に合わせて柔軟に対応できるよう、あらかじめ複数のプランを立てておけると安心です。
露出設定
ここでは光芒撮影での、露出設定のコツをご紹介します。
F値(絞り値)
F値はF6からF11程度を目安に絞ることで、光芒のやわらかさと風景の描写のバランスを取ることができるでしょう。絞りすぎると光芒の存在感が薄れる可能性があるため、注意が必要です。
関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説
シャッタースピード
シャッタースピードを遅くすることで、明るめの写真が撮りやすくなります。早朝や夕方の光芒撮影で十分な明るさを得られない場合は、遅めのシャッタースピードにしてみましょう。また、川のある森林などで撮影する場合、あえてシャッタースピードを遅くすることで、水の流れをやわらかく淡い光の流れのように表現することも可能です。ただし、手ブレには十分注意し、必要に応じて三脚を使いましょう。
関連記事:シャッタースピードとは?設定の目安や被写体に合わせたコツをご紹介
ISO感度
基本的にはオート設定で撮影し、晴天時はISO100からISO200、曇天や薄暮時はISO400からISO800程度が目安となります。光芒撮影では画質を重視したいため、できるだけ低めのISO感度が望ましいでしょう。
露出補正
白い砂浜や波しぶきなどで白飛びしそうな場合は、露出補正をマイナス方向に調整しましょう。反対に、逆光などで黒つぶれしてしまう場合は、プラス方向に補正します。光源の明るさと周辺の暗さのバランスを確認し、試行錯誤を重ねてながら最適な設定を見つけていくことが大切です。
ホワイトバランス
まずはオートホワイトバランスで撮影してみて、好みの表現になるようにホワイトバランスを調整してみましょう。暖色系のあたたかみを強調したり、寒色系でクールな雰囲気を演出したい場合など、ホワイトバランスを有効活用できます。特に朝や夕方の光芒撮影では、あたたかみのある太陽の光を表現できると、より印象的な作品に仕上がるでしょう。
関連記事:ホワイトバランスとは?基礎知識からクリエイティブな活用例までご紹介
光芒の印象を活かす構図

光芒を撮影する際は、逆光で画面の中央から上部1/3程度から光源や光芒が差し込むように構図をとると、印象的な仕上がりになります。光芒撮影では時間によって状況が刻々と変化するため、三分割構図や対角線構図などの基本的な構図を把握しておくと、状況に応じて柔軟に対応しやすくなります。
また、太陽を逆光で撮影する場合、光芒と光条を両方撮影できる場合があり、より複雑で美しい光の表現が可能になります。前景に山や木々のシルエットを配置することで、光芒の美しさがより際立つでしょう。
関連記事:逆光とは?その特徴と逆光を活かした撮影方法
レタッチで全体の印象を調える
明るすぎる部分を下げて光芒周辺の白飛びを抑制することで、より自然な仕上がりになります。暗すぎる部分を適度に持ち上げて、影になっている部分のディテールを見えるようにすると良いでしょう。彩度を微調整して夕焼けの色彩や光芒の明るさのバランスを取ることで、より印象的な作品に仕上がります。ただし、過度な調整は不自然な印象を与えるため、控えめに行うことをおすすめします。
光条を撮影するコツ

ここからは、光条をつくり出し、イメージ通りの写真を撮影するためのコツをご紹介します。夜景の街灯や太陽光などの強い光源を利用し、絞り値や露出設定を工夫することで、ドラマチックなアクセントになるでしょう。
絞りを絞る
光条を発生させるには、F8からF16程度を目安に絞りを絞ってみましょう。点光源の周囲に光条がはっきりと見えやすくなります。ただし、F22など絞り過ぎると、逆に回折により全体的にぼやけてしまう可能性があるため、絞り過ぎには要注意です。
F値以外の露出設定
F値以外にも、シャッタースピードやISO感度など、露出をコントロールするための設定を確認しておきましょう。
シャッタースピード
光条撮影では、基本的に手ブレしない範囲でシャッタースピードを設定し、必要に応じて三脚を使用します。夜景では1/60秒以下になる場合が多いため、三脚を用意しておきましょう。
ISO感度
昼間はISO100からISO400、夜景はISO800からISO3200程度が目安となります。ISO感度を高くし過ぎると、ノイズが目立ちやすくなる場合があるため、適度に設定しましょう。
露出補正
光芒の撮影と同様、光条の撮影においても、逆光で被写体が暗くなりがちなため、プラス方向に補正することで適度な明るさを確保できます。光源が強すぎて白飛びする場合は、マイナス方向に補正することで、全体のバランスを整えましょう。
ホワイトバランス
まずはオートホワイトバランスで撮影し、写真の仕上がりを確認しながら好みの色味に調整してみましょう。暖色系の色味を強調したい場合は、晴天などに設定することで、あたたかみのある印象になります。また、夜景をクールな印象で撮影したい場合は、電球などに設定することで青みが強調され、都市夜景らしい雰囲気を演出できます。
光条の印象を活かす構図

太陽など単一の光源に対して光条を表現する場合は、光源を画面の3分の1より上や中心からずらした位置に配置し、光条を対角線上や放射線状に伸ばすことで、メリハリのある印象を与えることができます。街灯など画面内に複数の光源がある場合は、パースペクティブを意識しながら構図をとることで、奥行きや整然とした美しさをダイナミックに表現できるでしょう。
関連記事:【初心者の方必見!】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!
シーン別の撮影方法
光芒や光条の撮影は、シーンに応じて異なるアプローチが必要となります。太陽光を光源とする場合や、夜景、風景など、それぞれに撮影のコツを確認してみましょう。
太陽光から光条をつくる

あえて光条を直接捉えることを避け、主題を強調するアクセントとして活用してみましょう。たとえば、逆光撮影で主題をシルエットにして光条との対比を強調することで、ドラマチックな印象を与えることができます。本格的な撮影では、PLフィルターで反射を抑制し、光条とのコントラストを調えることも効果的です。ただし、PLフィルターは光条を弱める場合もあるため、状況に応じて使い分けることが大切です。
夜景のアクセントに光条を活かす

街灯や建物の照明を光源とし、F11からF16を目安に絞ることで、美しい光の筋をつくることができます。整然とした街灯などは対角線構図などを意識してパースペクティブを強調し、空間的な広がりを表現します。また、画面全体に光源が点在する場合は、三分割構図なども意識するとバランスを取りやすいでしょう。ISO感度はISO1600からISO3200程度を目安に設定し、夜空を細部まで捉えながら光条とバランス良く収めましょう。
関連記事:【夜景の撮り方】きれいに撮影するためのコツをご紹介
光芒で神秘的な風景を演出

朝霧や山霧がある条件では、光芒がはっきりと立体的に見えやすくなるため、幻想的な雰囲気を演出できます。雨の日の翌日の晴天や水辺など、湿度の高い環境で早朝に撮影することで、美しい光芒を捉えることができるでしょう。森林の中で、木々の間から射し込む光芒も代表的な作例です。木々が密集しておらず、十分に太陽光が透過するポイントを探しましょう。光の柱の形状と風景のグラデーションを活かすため、縦構図も効果的です。
関連記事:【風景写真の撮り方】構図を活かしてダイナミックに!バランスよく撮るコツを解説
おすすめのタムロンレンズ
光芒や光条の撮影には、軽量・コンパクトで、光学性能に優れたレンズがおすすめです。風景撮影においては、広角ズームレンズや標準ズームレンズを検討してみましょう。また、タムロンのレンズは特殊なコーティング技術により、逆光下でもフレア・ゴーストを軽減し、鮮明な画像を得ることができます。
フルサイズ対応レンズ
-

-
16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 a064(Model A064)
市場で好評を得た17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)が進化した、第2世代「G2」モデル。ズーム倍率を拡大しながらも、軽量・コンパクトな設計を維持し、高画質を実現しました。さらに、AF性能を向上させるとともに、最新のレンズデザインにアップデートし、操作性を高めています。また、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てられるTAMRON Lens Utility™にも対応。初代の機動力と実用性を継承しながら、広角撮影の可能性をさらに拡げた16-30mm F2.8 G2。超広角ならではの表現を存分にお楽しみいただける一本です。
-

-
17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )
17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。
-

-
20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )
20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。
-

-
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。
-

-
28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD a071(Model )
これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを注ぎ込み、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)は誕生しました。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさを確保。広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域においても高い描写性能を実現します。
-

-
35-150mm F/2-2.8 Di III VXD a058(Model )
35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、広角端で開放 F2を達成し、準広角35mmから望遠150mmまで、ポートレート撮影で使用頻度の高い画角を1本でカバーします。大幅な大口径化と高画質を実現、リニアモーターフォーカス機構VXDにより高速・高精度AFを達成しています。新デザインの採用により、操作性や質感も向上しました。独自開発の専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズも可能になりました。
-

-
20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f050(Model )
F/2.8の明るさと高い近接撮影能力を合わせ持つレンズが登場。Model F050は超広角撮影を本格的に楽しめる20mmの単焦点レンズです。最短撮影距離0.11mまで寄れば、未体験の超広角世界を楽しむことができます。
-

-
24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f051(Model )
“驚異的に寄れる”広角単焦点レンズが登場。Model F051は広角写真のバリエーションを広げる焦点距離24mm、最短撮影距離0.12mを実現しています。撮影のフットワークを軽くする小型・軽量設計でスナップに最適なレンズです。
-

-
35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 f053(Model )
ミラーレス専用設計のソニーEマウントレンズシリーズに単焦点35mmが登場。Model F053はF/2.8と大口径でありながら最短撮影距離0.15mまでの近接撮影が可能。被写体が引き立つ美しいボケを楽しむことができます。
-

-
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD f072(Model )
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)は優れた解像力ととろけるボケ味。進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用した、コンパクトな中望遠マクロレンズです。
APS-C対応レンズ
-

-
11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )
11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。
-

-
17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )
17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。